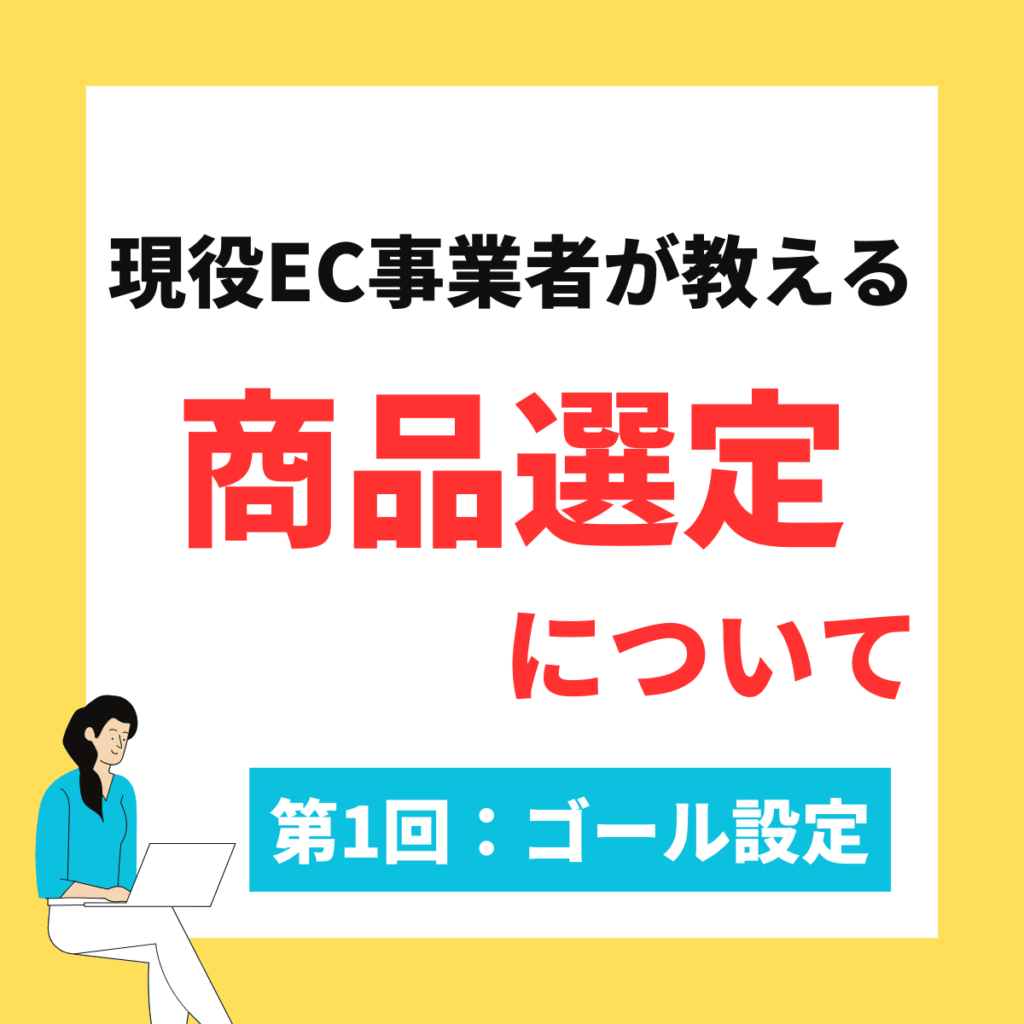
現役EC事業者の教える、「商品選定について」
(第1回ゴール設定)
ECの世界では「何を売るか」がすべての出発点です。けれど、多くの新規事業者が最初に失敗するのも、実はこの「商品選定」です。なぜなら、売れる商品と、売り続けられる商品はまったくの別物だから、です。
私たちは仕入れ代行として、数百社単位のショップの仕入れを支援してきました。そこで見えてきたのは、成功するショップと失敗するショップの“パターン”です。今回はその中でも核となる「商品選定のゴール」をテーマに、プロしか知らない裏側も交えながら解説していきます。
全て言われてみれば当たり前のことのように思えますが、驚くほどこのスタートの肝心なところを軽視している方が多いので改めてまとめてまいります。
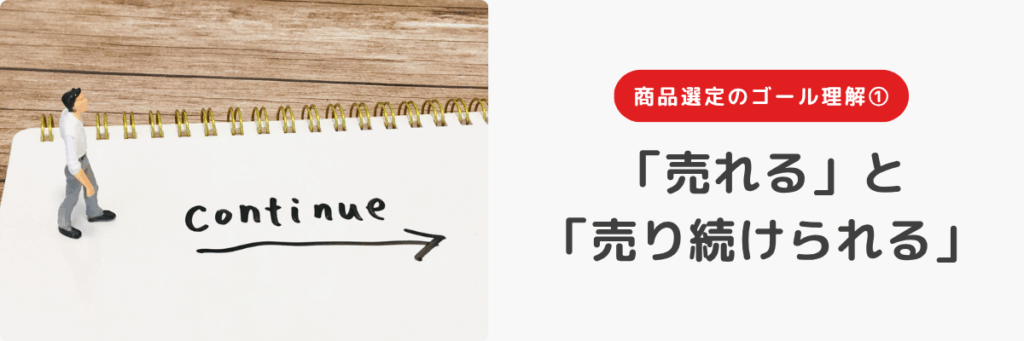
例えば、ある年にTikTokでバズったキッチングッズ。月に数千万売り上げた事例を知っています。
ところが半年後、売上はほぼゼロに。理由はシンプルで「みんなが飽きた」からです。倉庫には売れ残りの在庫が山積みになり、事業は撤退しました。
一方で、同じ時期に「消耗品+付加価値」を選んだ別の事業者は、3年経った今も安定して売上を積み上げています。仕入れは地味、広告効果も派手ではない。でも繰り返し買ってもらえる仕組みを選んだからこそ、事業が続いているんです。
仕入れの現場では「これ流行ってますよ」「今めっちゃ売れてますよ」という声が飛び交います。しかしプロの目線で言えば、むしろそこが危険信号です。“売れている”のと“売り続けられる”のは似て非なるもの。ここを区別できるかどうかが、事業の寿命を決めます。
むしろ、仕入れ代行業者から聞く、「今これめっちゃ売れてますよ」は「これはすぐに売れなくなる可能性が高いですよ」と解釈するくらいの慎重さでちょうど良いいくらいに考えています。

商品については様々な切り口がありますが、本項では大きく2種類に分けます。
短期利益型商品
トレンドに乗る。粗利は大きい。回収も早い。だが仕入れの読みを外すと一気に不良在庫。 例:流行ガジェット、SNSでバズった雑貨。長期ブランド型商品
常に一定の需要がある。育てるには時間がかかる。だがLTVが高く、安定経営につながる。 例:アウトドア用品、健康グッズ、楽器など。
強いショップは、この両方をミックスしています。もちろん、短期利益型のみでやる、という方もいらっしゃいますが、常にリスクを抱えながらの商売になるので、長続きはかなり難しいです。短期でキャッシュを作りつつ、長期でブランドを積み上げる。仕入れ代行をしていても、この二軸を意識している事業者は驚くほど少ないです。
だからこそ、ここを最初から設計できれば一歩抜きん出られるんです。

商品を探す前に「自分の店をどうしたいのか」を言語化するようにしましょう。
利益だけを狙うのか
リピート客を育てたいのか
ブランドとして確立したいのか
ここを決めていないと、仕入れの基準がブレて「なんとなく売れそうなもの」を買ってしまいます。結果は、在庫の山と資金繰りの悪化。これは私たちが一番よく見る“典型的な失敗”です。
逆に方向性が明確な事業者は、仕入れ相談も具体的です。「このカテゴリで10年食っていきたい」「OEMで独自ブランドにしたい」。こういう依頼は成功率が高いです。
これによって仕入れにかけるコストや商品選定が大きく異なります。もちろん、我々と相談しながらも、大いに歓迎です。
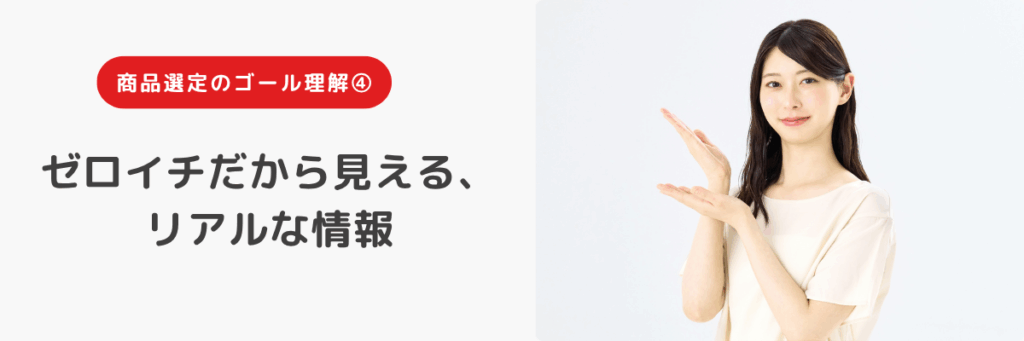
仕入れ代行はただの発注代行ではありません。私たちは現場で
「何が回転していて、何が死んでいるか」を毎日見ています。
例えば──
同じ商品でも「100個で仕入れるべきか、1000個で仕入れるべきか」
メーカー直か、卸経由か、どこで仕入れるのが一番利益率が高いか
OEMをかけるなら、どの段階で型代を回収できるか
こうした判断は、数字と現場感覚の両方が必要です。正直、ネットで調べても出てきません。
ここをショートカットできるのが、仕入れ代行を使う最大の価値だと思っています。
あるクライアントは、最初は「安く買えるならどこでもいい」という感覚でした。
ところが仕入れロットを誤り、1年でキャッシュがショート。私たちが再設計に入り、商品カテゴリをシフトしてからは2年連続で黒字化。これは「裏の情報」を反映した仕入れ計画を立てたからに他なりません。
まとめ
商品選定のゴールは「いま売れるものを探す」ことではありません。
売り続けられる仕組みを作ることです。
短期と長期、両方の視点を持ち、自分のショップの方向性を決める。そして仕入れ代行を“ただの作業代行”ではなく“戦略パートナー”として使う。
そうすれば、スタート時点から他のEC事業者よりも大きなアドバンテージを得られます。
次回は「市場調査の基本」。どのように需要を見極め、商品選定を数字で裏付けていくかを解説します。


